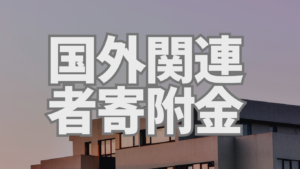中堅企業の国際課税リスク(BEPS 2.0)
近年、国際税務の世界で「歴史的な大転換」が起きています。それがOECDを中心に進められているBEPS 2.0(グローバルミニマム課税)です。

「うちのような中堅企業には、GoogleやAmazonのようなメガプラットフォーマー向けの税制は関係ない」と思っていませんか? 実は、その「油断」が将来的な経営リスクに直結する可能性があります。特に、成長過程にある中堅企業が直視すべき「第2の柱(グローバル・ミニマム課税)」について解説します。
1. 問題:自社は「対象外」という思い込み
現在導入が進んでいる「第2の柱」は、世界中のどこでビジネスをしていても、最低でも15%の税負担を求める制度です。
最大の問題は、多くの企業がこの制度の「影響範囲」を正しく把握できていないことです。「まだ売上1,000億円に届かないから大丈夫」と考えている企業でも、以下の理由で突然「当事者」になるリスクがあります。
- 為替変動の影響: 基準となる「7.5億ユーロ」は、円安が進むと日本円ベースでの閾値(いきち:境界値)が下がります。
- 急激な事業成長・M&A: 成長中の企業や、積極的な買収を行っている企業は、数年以内にこの基準を超える可能性があります。
- 事務負担の激増: 対象となった瞬間、世界中の子会社すべての実効税率を計算・報告する義務が生じ、経理体制がパンクする恐れがあります。
2. 根拠:グローバル・ミニマム課税(法人税法等の改正)
この制度の根拠は、OECDが公表したモデル規定に基づき、日本でも2023年度の税制改正で導入された「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」です。
これは、海外子会社の税負担率が15%に満たない場合、その差分を日本の親会社で上乗せして納税させる仕組みです。かつてのタックスヘイブン対策税制(CFC税制)よりもさらに広範で複雑な計算が求められるのが特徴です。
3. 解決策:2つの視点による「予防的対応」
まだ基準に達していない、あるいは基準付近にいる中堅企業が取るべき対策は、以下の2点です。
① 「7.5億ユーロ」境界線の継続的な監視
連結売上高が7.5億ユーロ(現在の為替レートで約1,380億円程度:2026年1月14日1 EUR = 約185 円)に近づいている場合、少なくとも直近4事業年度のうち2事業年度以上で基準を超えていないかを厳密にモニタリングする必要があります。 ※特に、海外売上比率が高い企業や、円安の影響を強く受ける企業は注意が必要です。
② 軽課税国における「実効税率」の予備計算
シンガポールやベトナム、タイなど、優遇税制(免税措置など)を受けている国がある場合、実際の税負担率が15%を割り込むことが珍しくありません。 「適用対象」になった際にどれだけの追加増税が発生するか、事前に簡易的なシミュレーション(セーフ・ハーバー規定の適用可否を含む)を行っておくことが、将来のキャッシュフロー管理において不可欠です。
まとめ
デジタル課税(BEPS 2.0)は、もはや巨大IT企業だけの問題ではありません。グローバルに展開する全ての中堅企業にとって、これは「成長の先にある不可避な税務インフラ」です。
直前になって慌てるのではなく、現時点での連結売上高の推移と、海外子会社の優遇税制の状況を棚卸しすることから始めてください。
貴社の直近の連結売上高と、主要な進出国の実効税率を基に、グローバル・ミニマム課税の影響を受ける「予備軍」に該当するかどうか、一度チェックしてみませんか?気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
- カテゴリー
- Risk Control